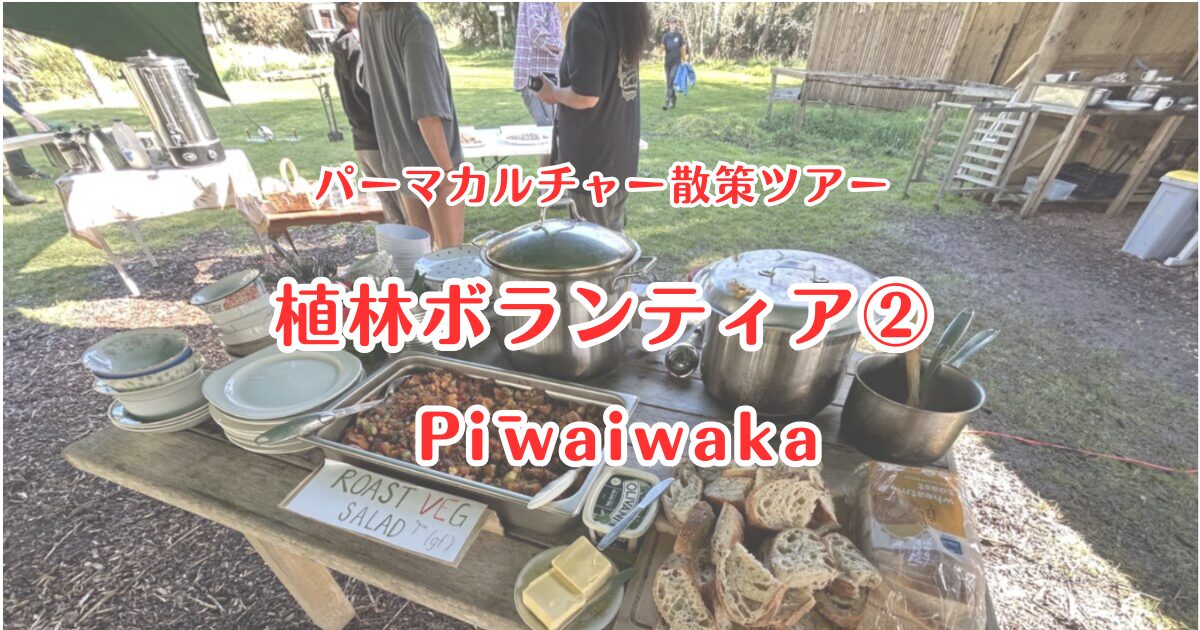ニュージーランドから「遊・暮・働・学」を共有します、パーマカルチャリストのまりこです!
娘の小学校の遠足で、私の住むワンガヌイ郊外にあるThe Eco-Schoolに行ってきました。
そこで学んだ、自然の循環のお話を共有したいと思います。
ニュージーランドの汚水問題

ニュージーランドのイメージは羊?
ニュージーランドといえば「酪農の国」というイメージがありますよね。
緑の牧草地に牛や羊がのんびり草を食べる、そんなのどかな風景が広がっています。
しかし実は、この家畜たちの糞が川を汚してしまうのです。
(牛のゲップが温室効果ガスの一因になる、とも言われます。)
「糞が?なぜ川を汚すの?」と疑問に思うかもしれません。
草食動物の糞は、少量であれば畑の肥やしになり、植物の栄養源として役立ちます。
でも、多すぎると問題になります。
動物たちは一日中草を食べ続け、たくさんの糞をします。
その一部は土にしみ込み、地下水を通って川へと流れていくのです。
もし木々があれば、深く張った根が余分な栄養分を吸い取り、水をきれいにしてくれます。
ところが、農場をつくるために木は切り倒されてしまいました。
自然豊かで人々が穏やかに暮らしているニュージーランド。
そんな国にも、人間の営みが引き起こした環境破壊の歴史があるのです。
遠足のメインイベントは、子どもたち一人ひとりが木を植える体験でした。
酪農王国ニュージーランドは「本当」?
私がEco-Schoolを訪れたのは5年前。
あの頃に植えられた小さな苗木たちが、いまでは立派に育ち、景色が大きく変わっていました。
そもそも、かつてのニュージーランドには人間すらいませんでした。
一面に森が広がり、鳥だけが暮らす無人の島だったのです。
やがて人間がやってきて、牛や羊などの家畜を連れてきました。
ペットやハチミツをつくるミツバチさえ、外から持ち込まれたものです。
つまり、ほとんどが外来種。(もちろん人間も。)
家畜を育てるためには、大量の餌が必要です。
そのため森は伐採され、広大な農場に姿を変えました。
現在の「酪農の国 ニュージーランド」は、人間がつくり出した風景なのです。
こうした環境の変化は、川の水質悪化や生態系の乱れなど、様々な問題を引き起こしています。
そこで注目されているのが、川沿いに木を植える取り組みです。
木の根が川岸を守り、水の浸食を防ぎ、さらに水をきれいにしてくれるからです。
人々は森を再生することで、失われた自然のバランスを取り戻そうとしています。
木を植えると、逆の問題も?
ただし、Eco-Schoolのオーナーはこうも言います。
「木を植えることには、別の課題もある」と。
木が増えると動物の住処や餌場になります。
それ自体は良いことのように思えますが、問題は「外来種」です。
外来種の動物たちもまた、再生された森に住み着きます。
ニュージーランドに連れてこられた外来種の動物たちは、天敵がいません。
安心して増え続ける結果、固有種の鳥の卵を食べてしまい、絶滅に追い込むこともあるのです。
実際に、もう戻らない鳥たちもいます。
そのため、外来種の数をコントロールする罠を仕掛けたり、様々な工夫が必要です。
けれども数はなかなか減らず、まさに「イタチごっこ」なのです。
森の再生に挑む現代
オーナーがここに住み始めた頃、広大な敷地にはほんの数本の木しかありませんでした。
私自身、娘が幼稚園の頃にこの場所を訪れたことがあります。
当時植えられた苗木は、いまでは大きく育ち、森らしい姿を取り戻しつつあります。
木々が根を張ることで土が安定し、川の流れは以前よりも澄みやかに戻ってきました。
森が再生すると、水だけでなく生態系全体が豊かになっていきます。
実際、このあたりには絶滅危機に瀕していた鳥たちも戻り始めています。
今年、私の庭にケレル(ニュージーランドの固有種のハト)が飛んできたのは、我が家だけの出来事ではありません。
街全体で続けられてきた森の再生の取り組みが、少しずつ実を結んでいる証拠なのだと感じています。
The Eco-School 日本人のWWOOF(ワークエクスチェンジに大人気のファームです)