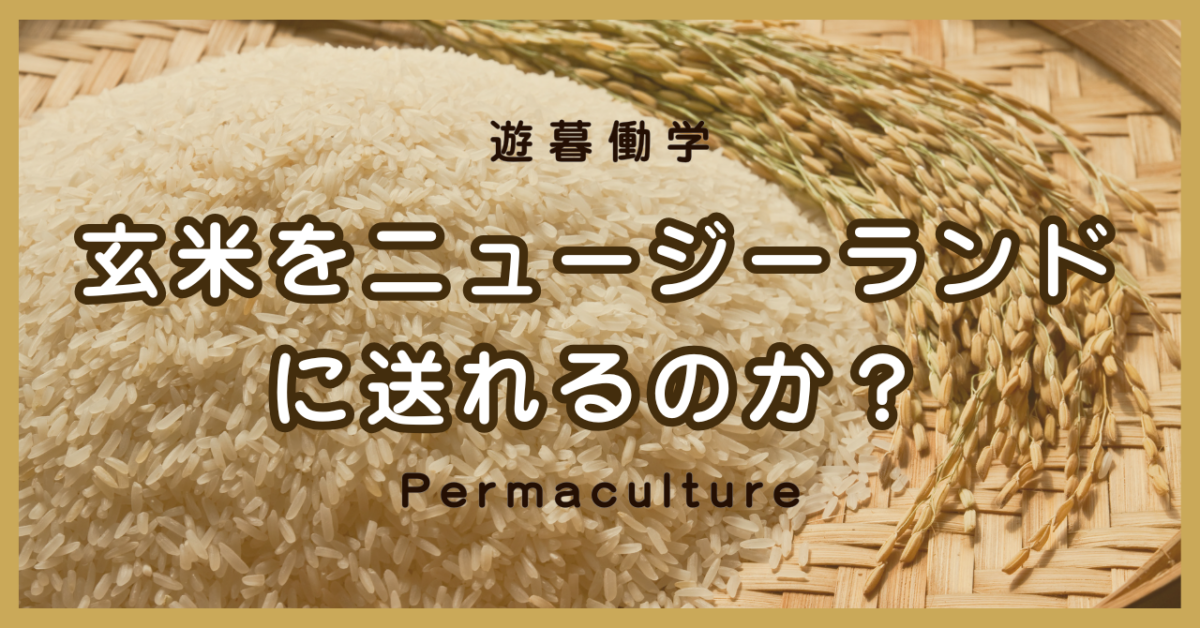ニュージーランドでお米を育てたパイオニア
「ニュージーランドでお米を育てている人がいる」とChat GPTに教えられ、希望を持った私。
しかし、日本から種籾(たねもみ、お米の種)を持ち込んで、田んぼを始めたパイオニア「櫻井博士」は、2024年11月に他界されていました。
私は20年、ニュージーランドに住んでいたのに、この地でお米を作っている人がいるとは想像をしたこともありませんでした。
気づいたのが、ほんの少し遅かった…
と、肩をガックリと落としていましたが、「もしかしたら、櫻井博士が誰かに種籾を託しているかもしれない」という望みを掛けて、持ち主探しの広告をSNSで拡散してもらいました。
…すると、なんとニュージーランドの日本人コミュニティー向け雑誌「月刊NZ」に、お米作りの特集が組まれていたという情報を得ました。
ちなみに、私が住むワンガヌイ市には、日本人が少ないこともあり、日本人コミュニティー雑誌は置いていません。
お米の持ち主、櫻井博士について
1938年神戸生まれ。建築音響工学博士。
カイワカでエコハウスや自然エネルギーを活用した発電など、自然と共生する持続可能な生活を実践。1990年代から米作りを始める。
現在、ニュージーランドでは米は商業生産されておらず、売られている米の100%が輸入品。『ニュージーランドでの稲作の可能性』として、地元メディアのStuffでも紹介された。
2024年4月逝去。 出典先 GEKKAN NZ
櫻井博士は1995年ごろから、ニュージーランドの北の方、ノースランドにあるKaiwakaという場所で、エコハウスに設計したご自宅で自給自足な暮らしを実践されていました。
ニュージーランドのお米は100%輸入に頼っていて、成育法が確立されていないながらも、実験を繰り返して、収穫できたのは4年後。初年は43kgだったのが、その後は最高で83kgになることもありました。
お米を育てる上で、重要なのは『太陽の光』つまり『熱』、ニュージーランドの夏は比較的涼しく、北海道に気候が近いことから、北海道の種(ゆきひかり)に注目されました。
ニュージーランドで稲の多年草栽培を実験し、田植えをしないで持続可能な栽培、つまりサスティナブルに米作りができるよう研究をされていました。
近年では、お米を購入しなくても、年間を通して自分の食べる分を賄えるほどに栽培、収穫をされていたそうです。
ニュージーランドで米づくり、敵はアイツ
お米の敵といえば、スズメ。日本の田んぼの風景にはカカシが付き物です。
しかし、稲はやがて実がつくと、その重さで穂が垂れるので、スズメにとって米をついばむには、難しい角度になるので、全滅はしません。
なので、ニュージーランドで気をつけなければならないのは、

プケコ
ニュージーランドのお土産グッズにもなっている青い体が美しいプケコですが、
あまり飛ぶことをしないプケコは、下からも攻撃してくるので、対策が大変です。その体も、口のサイズもスズメと比べると巨大ですので、被害は相当だと思われます。
それから、ネズミ
ネズミ対策として、自然農のパイオニアである福岡正信氏(わら一本の革命の著者)が考案した「粘土団子」で種を固めても、ネズミはお構いなしに種を食べてしまいます。
もし、私が米種を入手できることがあれば、ネズミ対策の強化が必須だと分かりました。
(庭にプケコは居ないので)
事前に知ることが出来て良かったです。
土とともに生き、未来の食を自分たちの手で守る
「稲はその土地の気候を記憶している」
種は、毎年同じ根や種を使うことで、その土地の風土を記憶して、その土地に適した種子に改善されていきます。なので、毎年育てて未来に受け継いでいくことが望ましいのです。
「いずれ、米の輸入が困難になる時代が来る」
そう、櫻井博士は危惧しておられたようです。
日本では、今年も米不足問題が深刻になっていますね。今なら、その意味を実感しますよね。
「土とともに生き、
未来の食を、自分たちの手で守る」 by 櫻井博士
ニュージーランドでも、私たちの手で、しっかりと米を受け継いでいく。
私が、そんなお手伝いができたらいいなと思います。
参考先、(Stone Soup)(YouTube)(YouTube2)